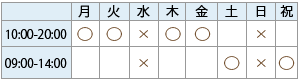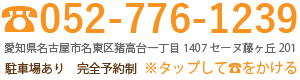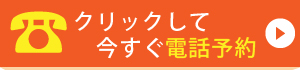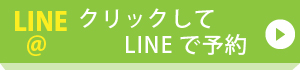ブログ
2017年01月17日
今日は数年前に診た患者さんの症例です。
【症例者】
年齢:13歳 性別:男性 職業:中学1年生 スポーツ:軟式野球(9月~1月まで駅伝部も兼ねる)
【現病歴】
両膝関節痛
12月よりランニングをすると両膝関節前面に痛みが生じた。12月9日当院し、物理療法・運動療法等を施行。2月に入り期末試験などで運動量が少なくなったため順調に回復してきていたが、3月に入り部活動が本格的に始まりランニングにより再び痛みが強くなり始めた。
【評価(3月3日時点)】
・圧痛(+):脛骨粗面(やや右>左) ・安静時・歩行時痛(-) ・走行時・屈伸時痛(+)
・熱感・腫脹(±):脛骨粗面(右>左) ・不安定性(-) ・SLR:右60°左70°
・ROM:膝屈曲(右120°左130°)膝伸展(右左0°)、足関節背屈(踏み込み時)(右20°左20°)
・MMT:股関節屈曲3レベル(右=左) ・Thomas test(+) ・ダイナミックアライメント:knee in-toe out
【メカニズム】
現病歴、所見よりOsgood-Schlatter病と推測する。この患者の場合、内的要因としては股関節屈曲、足関節背屈の可動域制限があり、しゃがみ込み動作においても、踵を着くことができない。これにより骨盤後傾になり、身体重心が後方に移り膝伸展モーメントが増大していると考えられる。外的要因としては昨年9月から本年1月まで野球部と駅伝部を兼ねていたということで、アスファルト上を1日平均7~8㎞を走行しており、環境と運動量の問題が考えられる。
【治療プログラム】
- 低周波(15分)・・・疼痛および炎症の軽減
- 手技、ストレッチ(7分)・・・股関節周囲筋・下腿の筋緊張の除去、股関節・足関節・膝関節の可動域の拡大
- 運動療法・・・股関節ストレッチ→バランスボール、セルフストレッチ
- 筋力強化→SLR.、Calf raise 、股関節周囲筋
※解説…基本的には走りすぎですよね。中学生は成長期なので、身長が伸びる際に筋肉も引っ張られるため筋肉が硬くなる時期です。この患者さんも太ももの筋肉の使い過ぎで、膝の痛みにつながっているようでした。この患者さんはストレッチ指導によりかなり改善されました。
特に中学生くらいはストレッチが大事だと思います。ストレッチのやり方が分からない方は、是非当院にお越しください。
ブログ
2017年01月16日
私が以前担当した患者さんの症例を書きます。専門用語が多いので最後に解説します。
【症例者】
年齢:12歳 性別:男性 職業:小学6年生 スポーツ:硬式野球(リトルリーグ、ポジションは主にピッチャー)
【現病歴】
右肩関節痛
11月中旬より、投球時に右肩関節後方に痛みが現れた。11月29日に当院来院。本人の希望もあり整形外科を紹介し、12月3日に受診。「右野球肩、Loose shoulder」と診断され、約1ヵ月の投球禁止と肩甲帯の筋力強化の指示を受けた。
【初期評価】
視診:右肩下制、円背 安静時痛(-) 圧痛:棘下筋、小円筋 前方引き出しテスト:右(+) 左(±) MMT:外転、屈曲、内旋、外旋すべて3レベル ROM:肩外転:右170°左180° 内旋:右45°左70° 外旋:右90°左100°
投球フォーム特徴:ワインドアップ期の体幹後傾、早期コッキング期の肘屈曲不足および肘下がり(
【メカニズム】
左側の不安定性が軽度であることから、後天的に投球が痛みの原因であると推測できる。損傷機序は、肩関節の位置が外転と外旋の組み合わせで、上腕骨頭が間接的な「てこ」の作用が反復活動され、前方に移動し障害が発生したと考えられる。要因としては、投球数過多による腱板機能の低下、それによる肘下がりなどフォームの問題、体幹の片側性の筋緊張の亢進などがある。この選手の場合についても肩甲骨の可動性の低下、右体幹機能の低下が見られた。それにより挙上時に肩甲上腕リズムが乱れ、肩甲上腕関節の剪断力が増加し肩への負担の増加に繋がっていたと考えられる。
【治療プログラム】
①肩腱板筋力と肩甲骨安定化機構の改善 ②体幹及び下半身のバランス強化 を図るため別紙の通りリハビリプログラムを作成した。
☆リハビリプログラム
<第1週目(12/6~12/11)>
①物理療法・・・痛みと炎症の軽減
・干渉波(15分間) ・背部マッサージ、穏やかな右肩関節モビリゼーション
②可動域訓練・・・痛みのない可動域の再確立
・振り子運動(5分間) ・棒体操(痛みのない範囲で5分間)
③筋力強化・・・筋萎縮の防止
・等尺性運動(壁を使い、屈曲・外転・伸展・内旋・外旋 各5秒間×10)
<第2週目(12/13~12/18)>
①物理療法・・・最小の疼痛と圧痛の状態
・干渉波(15分間) ・背部マッサージ、右肩関節モビリゼーション、肩甲帯ストレッチ
②可動域訓練・・・正常可動域
・棒体操(5分間) ・スイスボールにて肩甲帯ストレッチ(20×3)
③筋力強化・・・MMTで外転、屈曲、内旋、外旋すべて4レベル以上
・チューブ(屈曲・外転・伸展・内旋・外旋 各20×3)
<第3週目(12/20~12/25)>
①物理療法②可動域訓練・・・第2週目と同じ
③筋力強化
・チューブ(屈曲・外転・伸展・内旋・外旋 各20×3) ・1kgのダンベルを用い肩甲骨安定化機構のトレーニング ・バランスクッション(片足立ち 両側5秒間×10、スクワット20×3)
<第4週目(12/27~12/30)>
①物理療法②可動域訓練・・・第2週目と同じ
③筋力強化
・チューブ(屈曲・外転・伸展・内旋・外旋 各20×3) ・1kgのダンベルを用い肩甲骨安定化機構のトレーニング ・バランスクッション(クッションを二つ並べ片足立ちで移動 20×3、片足スクワット各10×3)
【結果】
1月7日に来院し評価をしたところ、不安定性の左右差、肩甲骨の可動性の低下、右体幹機能の低下、は消失した。1月8日、9日に50~70%の投球を行ったが痛みはなかった。
※解説
投げすぎにより肩の関節が緩くなる症状でした。痛みにより投球フォームを崩し、関節に負担をかけ悪循環の状態になっていました。しばらく投球は禁止し主に体幹トレーニングを中心にリハビリを行いました。痛みは徐々に緩和され、投球フォームも安定し肩に痛みが出なくなりました。
ブログ
2016年12月17日
こんにちは、接骨院三幸堂の後藤です。
開院して2週間ほど経ちました。
もともと私のところには腰や肩の痛みで来られる方が多かったのですが、
意外に今のところ、新患さんは膝の痛みの方が多いです。
一人の方は、
昔、足首を骨折⇒ 足首周囲の筋力低下⇒ アーチ(土踏まず)の低下⇒
回内足(足首が内側に倒れてしまう)⇒ 歩くたびに膝の外側が痛くなる
他の方は、
昔、左肩を何回も脱臼⇒ なるべく左手を使わないようにしていて体が左側に捻転⇒
体が左に回旋しているため、それにつられ右膝に付着する筋肉が引っ張られ炎症。
上記が痛みを作りだした大まかな流れだと考えていますが、お二人とも手首の骨折や婦人科系の
ご病気があったり、まだまだ様々な問題があったようです。
私のところでは、このような問題を一つ一つ解消していき、改善を目指していきます。
私の見かたが必ずしも正解とは限りませんが、問診、検査でいろいろな情報をとり、少しでも早く
患者さんによくなっていただきたいと常に考え施術しています。