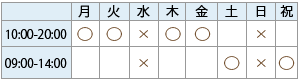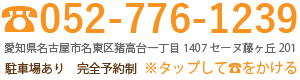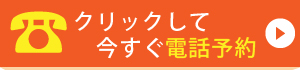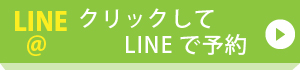朝食が夜の眠りを決める?|よく眠るための「朝ごはん戦略」
ブログ
2025年06月21日
そんな悩みを抱えている方は少なくありません。
実は、こうした睡眠の問題の多くは、“夜”ではなく“朝”に原因があるのをご存じでしょうか。
本記事では、体内時計や睡眠ホルモンのしくみに基づき、「朝ごはんこそが良質な睡眠をつくる第一歩」という視点から、実践的な改善策をご紹介します。
さらに、筆者自身が栄養と睡眠を意識した生活を始めた経験も交えてお伝えします。
1|眠りの準備は“夜”ではなく“朝”に始まっている
私たちの体は、約24時間のリズムで動く「体内時計(サーカディアンリズム)」を持っています。
この体内リズムが整っていると、朝はスムーズに目覚め、夜には自然と眠気が訪れます。
このリズムの要となるのが、「セロトニン」と「メラトニン」という2つのホルモンです。
▷ セロトニン(昼のホルモン)
- 朝〜日中に活発に分泌される
- 気分の安定や集中力に関与
- 夜の「眠気ホルモン」の原料になる
▷ メラトニン(夜のホルモン)
- セロトニンを材料として夜に分泌される
- 光を遮ることで分泌が促進される
- 眠気を誘い、自然な入眠をサポート
つまり、日中にセロトニンがしっかり作られていないと、夜になっても眠りに必要なメラトニンが十分に出てこないというわけです。
2|セロトニンを作る材料は「朝食」にある
セロトニンの材料となるのは、食事に含まれる「トリプトファン」という必須アミノ酸です。
トリプトファンを脳内でセロトニンへと変換するには、以下の栄養素も同時に必要です:
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| トリプトファン | セロトニンの原料 | 卵、納豆、まぐろ、チーズ、バナナなど |
| ビタミンB6 | トリプトファン代謝をサポート | 鶏むね肉、まぐろ、玄米、にんにくなど |
| 炭水化物 | 吸収を助ける | ごはん、パン、バナナ、オートミールなど |
| マグネシウム | 神経の興奮を抑える | アーモンド、ひじき、豆類など |
| 鉄・亜鉛 | 酵素の働きを補う | レバー、赤身肉、牡蠣など |
これらを朝のうちにしっかり摂ることで、日中の覚醒状態が安定し、夜の睡眠ホルモンの分泌にもつながります。
3|筆者の体験|サプリから始めて、朝食で変わった睡眠
私自身、数年前までは「眠りが浅い」「夜中に目が覚める」といった悩みを抱えていました。
その頃は、まずできることから始めようと、ソイプロテイン、マルチビタミンミネラル、トリプトファン、αリポ酸、バレリアンなどのサプリメントをいろいろ試していました。
体に合うものを選べば、確かに一定の効果は実感できましたし、サプリに頼ることへの違和感も特にありませんでした。
ただ、ある時期から朝食を少しずつ整えるようになり、「栄養を日々の食事で摂れているな」と実感できるようになったことで、
自然とサプリを飲まない日が出てきました。やめた理由は「めんどくさくなっただけ」で、飲まなくても問題ない状態になっていたのです。
今では、必要なときだけ気軽にサプリを活用するスタンスに落ち着いており、
基本は「食事から整える」ことをベースにしています。
4|おすすめ朝食例|眠りの質を上げるレシピ
「朝は時間がない」「食欲がない」という方も、以下のようなスタイルから取り入れてみてください。
✔ 和風スタイル(バランス重視)
- ごはん
- 納豆 or 卵かけごはん
- 味噌汁(具に豆腐・小松菜など)
- バナナ
✔ 洋風スタイル(手軽に実践)
- 全粒粉パン or オートミール
- ゆで卵 or チーズ
- ヨーグルト+はちみつ
- バナナ or ナッツ
✔ 忙しい朝に(時短スタイル)
- プロテイン+豆乳+バナナのシェイク
- オートミール+ヨーグルト+フルーツ
大切なのは「何を食べないか」ではなく、「何を組み合わせて食べるか」です。
5|朝食をとる「タイミング」も重要
セロトニンは「光+咀嚼」で活性化します。
そのため、朝起きてから1時間以内に朝食をとるのが理想です。
また、可能であればカーテンを開けて太陽光を浴びながら食べましょう。
こうすることで、体内時計がリセットされ、夜にメラトニンがしっかり出る準備が整います。
6|サプリメントとの上手な付き合い方
朝食で十分な栄養を摂るのが基本ですが、忙しい日や体調がすぐれない日は、無理せずサプリメントを使っても構いません。
以下のようなサプリが、眠りの質を高めるサポートになります:
- トリプトファン+ビタミンB6の組み合わせ
- マグネシウム、鉄、亜鉛などのミネラル系
- プロテイン(動物性+植物性)を活用してタンパク質補給
ただし、「サプリを飲めば眠れる」は大きな誤解。
サプリメントはあくまで「補助」であり、生活の土台が整っていてこそ効果を発揮します。
7|夜の眠りを整えたいなら、まずは“朝”を変える
多くの人が睡眠改善のために、
- 夜のスマホを控える
- 睡眠アプリを試す
- 寝具を買い替える
といった対策を取ります。もちろんこれらも有効ですが、もっと根本的に効くのが「朝の習慣」です。
「光を浴びて、しっかり朝食をとる」
これができるだけで、体内時計は整い、ホルモンの分泌も自然な流れに戻ります。
まとめ|よく眠るための「朝ごはん戦略」
睡眠の質を上げたいなら、特別なサプリでも寝具でもなく、まずは「朝の食事とリズム」を見直すことが近道です。
✔ 朝ごはん戦略まとめ
- セロトニンは朝の光と朝食で作られる
- タンパク質+炭水化物+ビタミンB群がカギ
- 起床後1時間以内に朝食をとる
- 忙しい日はプロテインやサプリを補助に使う
- 習慣化することで夜の眠りが自然と深くなる
私自身も、「朝を変える」ことで眠りが大きく変わりました。
あなたもぜひ、明日の朝から一歩踏み出してみてください。
ゆっくり、自然に眠れる体は、毎日の朝ごはんから作ることができます。
監修:柔道整復師、栄養睡眠カウンセラー 後藤康之